日常の中にある紅型 ― 伝統と未来をつなぐ物語
2025.09.21
おはようございます。
いつも紅型を通して琉球文化に関心を寄せてくださる皆さま、本当にありがとうございます。
私たち城間びんがた工房の挑戦は、皆さま一人ひとりの好奇心と応援によって日々支えられています。
このホームページでは、ものづくりの現場や日常の風景、時にはイベントの様子をお届けしています。けれど、その中心にあるのは「日常そのもの」です。紅型は特別な日のためだけにあるものではなく、暮らしのリズムと深く結びついてきました。
正直な仕事を祈るということ
昔の琉球時代の職人たちは、毎朝、水で身を清めてから仕事に向かったと伝えられています。
「今日も正直な仕事をさせてください」――その祈りには、王族の衣装を染めるという誇りだけではなく、「自分に対して正直でありたい」という職人的な気質も込められていたのではないでしょうか。
どんなに小さな一筆であっても誤魔化さず、丁寧に積み重ねていく。そうした姿勢が、紅型の布一枚一枚に息づいているのです。

現代の令和7年、そのリズムを守ることは簡単ではありません。社会は速く変わり、工芸は効率や成果とは相性の良い営みではありません。けれどだからこそ、静かにコツコツと仕事と向き合える時間を持てることに感謝し、日々の営みを大切にしています。
例えば最近の体験ですが、私は型彫りに「ルクジュー」と呼ばれる島豆腐を乾燥させた下敷きを使います。これは弾力を自分好みに調整できる優れものです。油を塗れば弾力が保たれ、硬すぎれば水につけて少し戻すこともできる――ゴム板やシリコンマットにはない独特の良さです。
ある日、それを怠けて調整しなかったところ、一日で手が痛くなってしまいました。正直に準備と向き合うことの大切さを、こんな小さな日常からも教えられるのです。


戦後80年という節目に
今年は戦後80年という大きな節目の年です。
祖父は38歳で終戦を迎え、父は9歳で戦後を経験しました。焼け野原の中で祖父が工房を再開した姿を思うと、紅型は「美しいものを作る仕事」であると同時に、生きるための力だったのだと感じます。
祖父の時代には、自然から取った竹を道具にし、サトウキビの絞りかすを叩いて地染めを作り、レンガや身近なものを粉末にして顔料を作っていました。大豆の絞り汁で絵の具を溶き、アメリカ兵の捨てていったシーツを切り取って染める――そうして仕上げられた布には、説明しなくても伝わる「リアリティ」が宿っています。
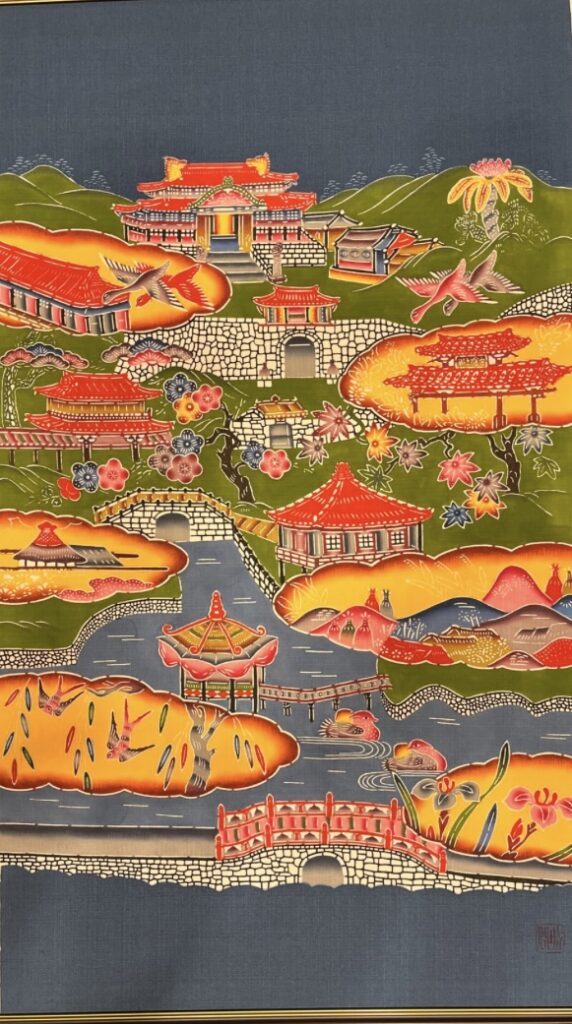
私は、そのリアリティに負けない作品を、現代の価値観に届けなければならないと感じています。16代目として工房を担ういま、問われているのは「これからの時代に紅型をどう伝えるか」です。伝統を守るだけでなく、日常に寄り添う形で未来へつなぐ挑戦を続けていきたいと思います。
参加してくださる皆さまへ
工房の取り組みは、私一人で完結するものではありません。
日々一緒に制作を続ける職人仲間たち、庭の何気ない風景を楽しんでくださるお客様、そして遠くからホームページを通じて関心を寄せてくださる皆さま。
この文章を読んでくださっている「あなた」も、すでにこの物語の一部です。
私たちが糊を置き、色を挿し、布を染めるように、読んでくださる皆さまの記憶や感覚の中にも紅型の物語は積み重なっていきます。ぜひ「参加者」として、それぞれの暮らしの中で物語を育んでいただければ嬉しいです。
日常の中の豊かさを
工芸というと、特別なものに思えるかもしれません。
しかし実際には、朝の光や潮風の匂い、通学路の景色――そうした日常の一瞬一瞬から紅型の図案は生まれています。
だからこそ、このホームページでは特別な展示やイベントだけでなく、日常の小さな風景もお届けしたいと思います。庭に咲く花、工房の静けさ、職人の手の動き。そこに宿る「生きた文化」の気配を、皆さまに感じ取っていただければ幸いです。


最後に
工房を支えてくださるすべての方に、改めて感謝を申し上げます。
80年前、戦後の混乱期に工房を再開した祖父も、9歳で戦後を迎えた父も、そして今を生きる私も――それぞれの時代に「紅型を続ける」という選択をしてきました。
そして、その選択を支えているのは、いつの時代も「見てくださる人」「共にいてくださる人」の存在です。
あなたがこの文章を読んでいること自体が、紅型の未来をつなぐ一歩であり、新しい物語の始まりです。





LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@275zrjgg

Instagram https://www.instagram.com/shiromabingata16/
公式ホームページでは、紅型の歴史や伝統、私自身の制作にかける思いなどを、やや丁寧に、文化的な視点も交えながら発信しています。一方でInstagramでは、職人の日常や工房のちょっとした風景、沖縄の光や緑の中に息づく“暮らしに根ざした紅型”の表情を気軽に紹介しています。たとえば、朝の染料作りの様子や、工房の裏庭で揺れる福木の葉っぱ、時には染めたての布を空にかざした一瞬の写真など、ものづくりの空気感を身近に感じていただける内容を心がけています。
紅型は決して遠い伝統ではなく、今を生きる私たちの日々とともにあるものです。これからも新しい挑戦と日々の積み重ねを大切にしながら、沖縄の染め物文化の魅力を発信し続けていきたいと思います。ぜひInstagramものぞいていただき、工房の日常や沖縄の彩りを一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

城間栄市 プロフィール昭和52年(1977年)、沖縄県生まれ。
城間びんがた工房十五代・城間栄順の長男として育つ。
学歴・海外研修
- 平成15年(2003年)より2年間、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州に滞在し、バティック(ろうけつ染)を学ぶ。
- 帰国後は城間びんがた工房にて、琉球びんがたの制作・指導に専念。
受賞・展覧会歴
- 平成24年:西部工芸展 福岡市長賞 受賞
- 平成25年:沖展 正会員に推挙
- 平成26年:西部工芸展 奨励賞 受賞
- 平成27年:日本工芸会 新人賞を受賞し、正会員に推挙
- 令和3年:西部工芸展 沖縄タイムス社賞 受賞
- 令和4年:MOA美術館 岡田茂吉賞 大賞 受賞
- 令和5年:西部工芸展 西部支部長賞 受賞
主な出展
- 「ポケモン工芸展」に出展
- 文化庁主催「日中韓芸術祭」に出展
- 令和6年:文化庁「技を極める」展に出展
現在の役職・活動
- 城間びんがた工房 十六代 代表
- 日本工芸会 正会員
- 沖展(沖縄タイムス社主催公募展)染色部門 審査員
- 沖縄県立芸術大学 非常勤講師
プロフィール概要
はじめまして。城間びんがた工房16代目の城間栄市です。私は1977年、十五代・城間栄順の長男として沖縄に生まれ、幼いころから紅型の仕事に親しみながら育ちました。工房に入った後は父のもとで修行を重ねつつ、沖縄県芸術祭「沖展」に初入選したことをきっかけに本格的に紅型作家として歩み始めました。
これまでの道のりの中で、沖展賞や日本工芸会の新人賞、西部伝統工芸展での沖縄タイムス社賞・西部支部長賞、そしてMOA美術館の岡田茂吉賞大賞など、さまざまな賞をいただくことができました。また、沖展の正会員や日本工芸会の正会員として活動しながら、審査員として後進の作品にも向き合う立場も経験しています。
私自身の制作で特に印象に残っているのは、「波の歌」という紅型着物の作品です。これは沖縄の海を泳ぐ生き物たちの姿を、藍型を基調とした布に躍動感をもって表現したものです。伝統の技法を守りつつ、そこに自分なりの視点や工夫を重ねることで、新しい紅型の可能性を切り拓きたいという思いが込められています。こうした活動を通して、紅型が沖縄の誇る伝統工芸であるだけでなく、日本、そして世界に発信できるアートであると感じています。
20代の頃にはアジア各地を巡り、2003年から2年間はインドネシア・ジョグジャカルタでバティック(ろうけつ染)を学びました。現地での生活や工芸の現場を通して、異文化の技術や感性にふれ、自分自身の紅型への向き合い方にも大きな影響を受けました。伝統を守るだけでなく、常に新しい刺激や発見を大切にしています。
最近では、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」など、世界を巡回する企画展にも参加する機会が増えてきました。紅型の技法でポケモンを表現するというチャレンジは、私自身にとっても大きな刺激となりましたし、沖縄の紅型が海外のお客様にも響く可能性を感じています。
メディアにも多く取り上げていただくようになりました。テレビや新聞、ウェブメディアで工房の日常や制作現場が紹介されるたびに、「300年前と変わらない手仕事」に込めた想いを、多くの方に伝えたいと強く思います。